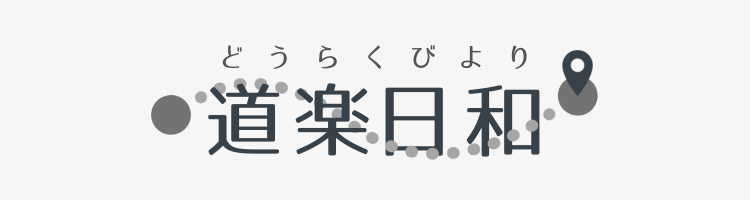線路の風景が呼び起こす“夏の冒険”
休日に知らない街を歩いていると、ふと胸の奥に少年時代の空気がよみがえる瞬間がある。道端の線路、少し湿った木々の匂い、遠くの空へ真っすぐ伸びる一本道――。
『スタンド・バイ・ミー』(1986)は、そんな情景を鮮やかに呼び起こしてくれるロードムービーだ。
この映画は、12歳の少年たちが“死体を探す旅”に出る、という一見物騒な出発点を持つ。しかし実際に描かれるのは、少年期特有のまっすぐな友情、まだ不安定な自尊心、そして「大人になること」への初めての戸惑いだ。原作はスティーブン・キングの『恐怖の四季』に収められた中編「The Body」。ホラー作家としてのキングとは少し違う、静かで繊細な筆致が映画全体に行き渡っている。
監督はロブ・ライナー。主要キャストにはウィル・ウィートン、リヴァー・フェニックス、コリー・フェルドマン、ジェリー・オコンネルら、若き日の面々が並ぶ。
舞台は1950年代のオレゴン州。乾いた夏の空気、雑木林のゆらめき、線路の金属が陽に照らされて白く光る風景——どのシーンにも、旅の匂いが漂う。私が各地を散歩しているとき、たとえば駅舎の裏手に伸びる非電化区間の線路を見つけると、ふとこの映画の世界を思い出す。少年たちが線路の上を歩く姿は、ただの交通インフラではない、「旅の象徴」としての線路を見事に描き出している。
彼らは重いリュックを背負い、汗を拭いながら、延々と続く線路を歩き続ける。歩くスピードは自転車や車に比べて遅い。その分、彼らの感情や友情が、風景の中でゆっくりと熟していく。その描写は、私たちが散歩中にふと昔の記憶を思い出すときの感覚に似ている。
初見の人にとって、『スタンド・バイ・ミー』は“少年たちが冒険する映画”という入口で楽しめる。一方、すでに観たことがある人にとっては、彼らの旅が「自分の少年時代」や「かつて歩いた道」を思い出させてくれる作品だ。
とりわけリヴァー・フェニックスが演じるクリスの存在は、何度観ても胸に響く。彼の成熟した演技は、映画を観た年齢が変わるたびに、違う深さで心に届いてくる。
また、物語の語り手である大人になったゴーディの視点によって「旅の記憶」が静かに語られる構成は、大人になってから散歩をすることの意味——“歩くことで、時々、昔の自分と再会できる”という感覚を思い起こさせる。これは本作の大きな魅力であり、再鑑賞の価値を何倍にも高めてくれる。
この映画には、旅の風景と歩くことの楽しさ、そして歩くことで生まれる“心の動き”が詰まっている。
日本のローカル線沿いを散歩していると、林の向こうから電車の音が聞こえてきたり、線路がゆるく曲がっていく先に何があるのか想像したりする瞬間がある。『スタンド・バイ・ミー』は、その“想像の旅”を普遍的な物語として見せてくれる映画だ。
散歩も旅も、目的地だけではなく“道中”が価値を持つ。そのことをあらためて教えてくれるのが、この映画なのである。
少年たちが歩いた線路は、人生の縮図でもある。まっすぐで単純に見えて、実は分岐や坂道があり、時に誰かと肩を並べて歩き、時に孤独になる。
映画の最後に語られる「子どもの頃の友だちほど、強く心に残る友だちはいない」という言葉は、人生のどの時期に見ても響く。それは観る人自身の旅路と共鳴するからだろう。
次の散歩で、ふと線路を見つけたら、この映画を思い出してほしい。“旅の始まり”はいつも、案外すぐそばにあるものだ。